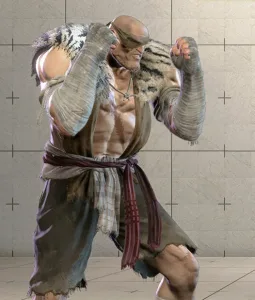皆さんこんにちは、ナツです!
先日Act9にて、ついに長年の目標としていたアルマスに到達することが出来ました!レジェンドを除くとマスター帯では最高ランクになるので、達成できてとても嬉しかったです。

さて、今回はアルマスを達成できたということで、筆者のアルマス到達までの過程を公開し、どれくらいの時間で達成したのか、各MR帯で何を意識すれば良かったのかを私なりに解説していこうと思います。
もちろん、ここに書いてあることが全てでは無いですし、もっと強い人は沢山いると思いますが、こういう過程や考え方もあるんだなと私の経験が皆さんの参考になれば幸いです。
この記事では、MR帯を以下の4つに分けつつ、「どんなMR帯か」「このMR帯で何を意識して取り組んだか」についてそれぞれ解説します。
- マスター昇格~MR1500
- MR1500~MR1600
- MR1600~MR1700(ハイマス帯)
- MR1700~MR1800(グラマス帯)
早速以下から本題に入っていきます!
①マスター昇格~MR1500

どんなMR帯か
マスター昇格のタイミングでは、MR1500からスタートしますが、初めは全く勝てずに連敗が続きます。ダイヤ帯を勝ち抜いてきた方たちですが、この連敗に耐えられず挫折してしまう人も少なくありません。個人差はありますが、大体MR1100~1200くらいで連敗が止まりはじめ、勝率50%付近に落ち着いてきます。
この帯域は、マスター帯でしっかり勝ち抜いていくためには、課題が残る帯域です。例えばバトルハブとかで少し対戦しても、「このコンボの上手さでどうしてこの帯域なんだろう?」と思うと1試合にBOを何度もしていたり、という感じで何かしら課題がある印象です。逆に言えば、課題さえ明確になれば動きが格段に良くなる帯域でもあります。
筆者は後述の3点を意識して取り組んだ際にグッと伸びたなと思いますので、紹介していきますね。
このMR帯で何を意識したか
コンボ選択の見直し
これがまず一番大きなポイントかなと思います。これまでずっと使ってきたコンボを見直し、もっとダメージが高いコンボはないか、起き攻めしやすいコンボはないかに着目して探し、練習しました。例えば、私がマスター昇格直後に使っていた中足キャンセルコンボは1600ダメージしか出なかったのに対し、見直し後は2000ダメージ出るようなコンボを選択するようにしました。試合中に何度もヒットさせる中足始動で400ダメージ上げていれば、1試合3回ヒットさせると見直し前と比較して1200ダメージの差が出るので、勝率に直結すること間違いなしです。
皆さんのキャラでも、まずは中足始動・大P始動・リーサルコンボなど、立ち回りで振る技・よく当てる始動技を中心に「火力重視」・「起き攻め重視」・「Dゲージ節約」の観点から一度整理して見直してみるのがおススメです。
各技ごとに綺麗に整理できなくても良いので、火力が欲しかったらコレ、Dゲージを節約したかったらコレというくらいざっくりで大丈夫です。
Dゲージの管理
コンボがある程度整理できてきたところで次の課題となるのがDゲージの管理です。以前のダイヤ帯突破の記事でも書いてはいるのですが、リソースの管理はとても大切だと思うので再度書いています。Dゲージが少ないからパリィを多めにして回復する、OD技を使わないはもちろん、Dゲージも体力も残っているので強気にキャンセルラッシュで攻めるのもDゲージ管理の一環です。
この帯域で陥りがちなのが、丁寧に立ち回ろうとするあまり、Dゲージが6本溜まったままだったり、相手に削られるだけになってしまうことです。どんなに一生懸命貯めたDゲージも使い道が無いと宝の持ち腐れなので、まずはラッシュして有利Fを取るところから始めてみましょう。

対空精度の向上
どのランク帯でも付きまとうポイントですが、しっかり対空を出せることは間違いなく勝率に直結するので、試合中に1回でも多く出せるように練習しましょう。私はランクマッチをやる前の5分間と対戦待ち受けの間を対空練習の時間として意識して練習していました。何気なくやっているだけでも無意識に出せる場面は増えていくので、数をこなして自分の手に馴染ませましょう。
②MR1500~MR1600
どんなMR帯か
MR1500までMR帯をやりこんでいる時点で相当強い部類に入っています。諸説ありますが筆者調べで全体上位7~8%程度と言われています。
MR1500に浮上してきてからは、更に相手も強くなり、甘えが許されなくなってきます。自分も相手も対空・コンボ選択はほぼ出来ているので、これまでの帯域よりも細かい差が勝率に響く帯域だと思います。
このMR帯で何を意識したか
自キャラで頻出する読み合いの整理
MR1500帯を抜けるにはこれが一番大きいポイントだったかなと思います。
自分の使っているキャラでどの技・連携が有利Fを取れるのか、有利Fを取った後に暴れつぶしからコンボに行ける連携はどれか、有利から暴れてこない相手には投げを重ねる・シミー出来るようにするなど、自キャラを使っていて発生する読み合いをこのタイミングで整理しました。
もちろん、全て整理したとおりに出来るわけではないですが、基本を抑えておくことで、整理できていない相手よりも優位に読み合いを回すことが出来るので、やって損はないはずです。

セットプレイの習得
これはキャラによると思いますが、セットプレイが豊富にあるキャラはそれらを習得・バリエーションを増やすことで攻めがさらに強化されるので、おすすめです。私の場合は使用キャラがラシードということもあり、セットプレイが非常に多く、持続中段や+4,5F投げ状況に持っていけるフレーム消費を一通り習得しました。
セットプレイの良い所は起き攻めなどで強い状況を安定して作れるところなので、自キャラの強みを生かすためにもセットプレイの習得はこの辺りで行うと良いかなと思います。
③MR1600~MR1700(ハイマス帯)

どんなMR帯か
MR1500帯よりも更に甘えが通らなくなる帯域です。
細かい差や1ミスが勝率に直結するので、個人的に何をすれば抜けられるのか明確な答えが見つからず、一番苦戦した帯域です。
このMR帯で何を意識したか
難易度の高いセットプレイの習得
1500帯の時に整理したセットプレイのうち、難易度が高いため後回しにしていたセットプレイを習得し、試合で使えるようにしておきました。例えば、ラシードのセットプレイであれば、詐欺飛びルートやウイングストローク起き攻めなどのセットプレイですね。難しいけど使われるセットプレイは相手も対応しづらい強みがあって使われているので、これらの習得で、攻めがかなり楽になりました。
防御面の強化
防御面の強化ですが、特に仕込みの部分をしっかり出来るようにトレモで練習しました。例えば、キャンセルラッシュにOD無敵を仕込んでおくのをサボらないようにしたり、詐欺飛びに対して立ガード+小パンを仕込んでおいたりというように、読み合いを拒否したり両対応できるテクを調べて取り入れるようにしました。

④MR1700~MR1800(グラマス帯)

どんなMR帯か
アルマスに向けた最後の関門。相手もやりこんでいるため、知らないマイナーセットプレイや起き攻めに出会ったりします。何が悪いから負けたとはっきり分かる試合よりも、選択は合ってたけど結果的に負けたという試合もちょこちょこあるイメージです。
このMR帯で何を意識したか
コンボ・セットプレイ精度の向上
グラマス帯を抜けるために一番やったのはこれです。いろいろ立ち回りを変えるなどやってみましたが、結局相手に触ったときにダメージを取り切れないミスの方が影響が大きいので、各種精度の向上に努めました。
セットプレイで試合中ミスをしたら、そのセットプレイを1P/2P側両方で10回連続で成功させるまでトレモに籠ったり、小パン重ね・投げ重ねにミスが無いようにひたすら重ねの練習をしたり…ととにかく精度を上げることを徹底しました。
これはかなり速攻性があり、やり始めて1週間くらいでアルマス到達出来ました。基礎が大事なのは本当にその通りだと痛感しましたね。
【まとめ】 停滞しても、諦めなければ必ず道は開ける
ここまで、私のアルマスまでの道のりを紹介させていただきました。
私自身、初マスターからアルマス到達まで約1年半かかりましたし、特にMR1600帯では「何をすれば勝てるんだ」と一番苦戦しました。 皆さんも今、特定のランク帯で勝てなくなり、伸び悩んでいるかもしれません。
しかし、停滞しているということは、そこに必ず「伸びしろ」があるということです。 コンボを見直したり、セットプレイを覚えたり、精度を高めたり…一つ一つの課題をクリアしていった結果が、アルマス到達でした。課題すら分からなくて停滞し続けたりもしましたが、それでも徐々にMRは上がっていきました。
この記事が、あなたの壁を破るための「次の一歩」の参考になれば幸いです。 時間はかかっても、続ければ必ず結果はついてきます。一緒に頑張っていきましょう!